まずは健康が最優先。でも「お金の話」は避けられない
夫の初期の症状は、典型的な“うつ”のものでした。夜眠れない、食欲がない、仕事のことを考えると激しい動機、涙が自然と流れる——。
夫は教員の中間管理職という立場だったので、学校全体のスケジュールの管理や計画、行事での司会進行、担任教師への指導。欠席した教員の代わりに授業をしたり、育休などの理由で担任が長期不在になったクラスの担任を臨時で請け負うこともあります。日々の膨大な業務をこなしながら子どもや保護者の対応もします。そのため精神的に追い詰められることが多い仕事です。
病院に行き、正式に「うつ病」と診断され、まずは3か月の「病気休暇」に入ることになりました。
このとき、最も不安だったのが「収入はどうなるの?」ということでした。子どももまだ小さいし、住宅ローンも残っている。我が家の家計は、夫の収入がベースになっていました。
教員の病気休暇と休職制度の流れ
調べてみると、公立学校の教員にはしっかりとした休職制度が整っていました。特に、精神疾患による休職は今の時代、決して珍しいことではないようで、制度としても対応がされています。
【1】病気休暇(最長90日)
まずは3か月間の病気休暇。この間は給与が満額支給されます。保険料や税金なども通常通り引かれますが、手取りの金額はほぼ変わりません。もちろん、給食費は給与から引かれなくなり、交通費は支給されなくなります。この期間は、夫も少しホッとして療養に集中できたと思います。
【2】休職(最長3年間)
病気休暇が終わると、「休職」という扱いになります。休職中は次のように給与が変わります。
- 最初の1年6か月:給与の8割が支給
- それ以降:給与は支給されないが、傷病手当金が健康保険から支給(標準報酬月額の2/3)
つまり、いきなり無収入になるわけではありません。初めの1年半は8割の給与があるため、大きなライフスタイルの変更はせずに済みます。
そして、1年半を超えて療養が続く場合でも、「傷病手当金」が支えになります。これは健康保険から支給されるもので、標準報酬月額の3分の2相当が支給されるのです。
さらに、うつ病などの精神疾患で休職が長期化した場合、発症から1年6か月(=1年半)を経過すると、「障害年金」の申請が可能になります。これは「働くことが難しい状態が続いている」と医師に判断された場合に支給される年金で、初診日が厚生年金や国民年金に加入中であれば、等級に応じて月額の支給が受けられる可能性があります。
我が家もこのタイミングで障害年金のことを知り、主治医に相談を始めました。制度は少し複雑で、提出する書類もたくさんありますが、該当する方にとっては大きな経済的支えになるものなので、忘れずに早めに検討しておくことをおすすめします。
実際にかかったお金と家計の見直し
収入が減ることは事実です。そこで我が家では、以下のような見直しを行いました。
- サブスクリプションの解約(動画、音楽、新聞など)
- 保険の見直し(掛け捨て型で見直せるものは調整)
- 食費の工夫(外食を減らし、買い物を計画的に)
- 格安スマホに変える(Ymobile、UQmobile、楽天mobile等)
しかし、実際に生活してみると、思っていた以上に通院費や薬代がかかり、家計にじわじわと響いてくることを実感しました。
そんなときに利用をおすすめしたいのが**「自立支援医療制度」です。これは精神科などの通院にかかる医療費の自己負担額を原則1割に軽減してくれる制度**で、認定されれば非常に助かります。自治体に申請して承認される必要がありますが、経済的な負担を大きく減らすことができます。
ただ、注意点として、休職を延長するには3か月ごとに診断書を提出しなければならず、そのたびに医師に書いてもらう診断書代(夫が通院している病院では7700円でした)もかさんでいきます。この費用には自立支援医療制度は適用されないので実費になります。療養が長引く場合は、このような“見えない支出”にも備えておくと安心です。
支える家族も、無理をしないことが大切
うつ病は、「すぐに治る」病気ではありません。薬やカウンセリングで症状が安定しても、再発することもあります。だからこそ、長期的な視点で構えることが必要です。
そのためには、支える家族自身も息抜きが必要だと痛感しました。私も最初の頃は、「家計を守らなきゃ」「夫を支えなきゃ」と頑張りすぎて、体調を崩しかけたことがありました。
今は、週に1度は自分の好きなことをする時間を確保するようにしています。カフェで読書をしたり、友達と話したり、小さなことでもリフレッシュになります。
まとめ:制度を活用して、焦らず向き合う
夫がうつ病で休職してから、家計のこと、生活のこと、心のこと——本当に多くのことを見直す機会になりました。
「教員だからこそ制度が整っている」という安心材料があったことも事実です。公務員として働いている方は、思っている以上にしっかりとした保障があります。
焦らず、制度を活用しながら、「今できることを少しずつ」。支える側も、自分の心と体を大切にしていく——そんな日々を過ごしています。
この体験が、同じような不安の中にいる方の、少しでも参考になれば幸いです。
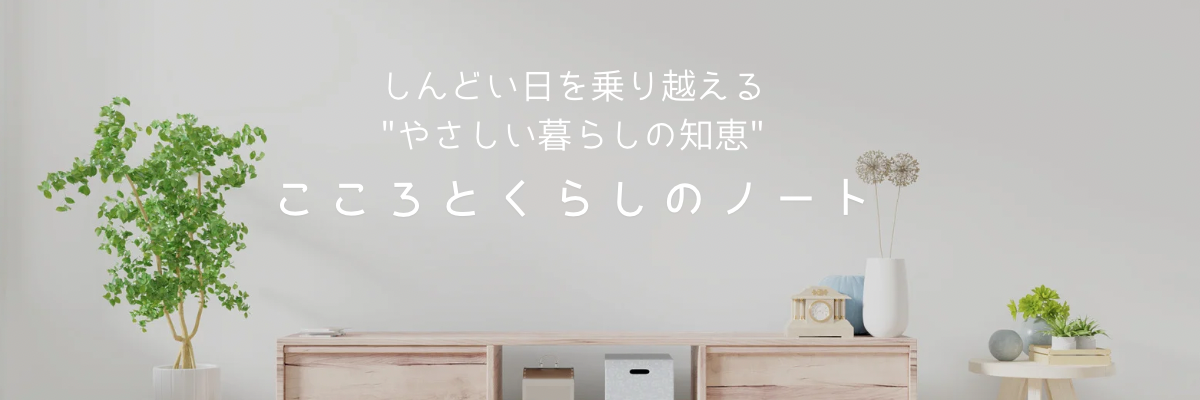


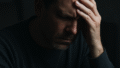
コメント