家族がうつで休職すると、支える側もしんどくなります。
私自身「弱音を吐いたらいけない」「私が頑張らなきゃ」と思い込み、気づけば心が限界でした。
この記事では、うつの夫を支える中で感じた本音や、誰にも言えなかった気持ちを正直に書いています。
同じ立場の方が、「私だけじゃない」と思えるきっかけになればうれしいです。
「逃げ場がある」と知っておくだけでも楽になります。
■「いいパパ」と「怒るパパ」…子どもの混乱と、私の葛藤
夫は、気持ちが安定しているときは、本当にいいお父さんです。
笑顔で遊び、子どもの話にも丁寧に耳を傾け、子どもも心から楽しそうにしています。
でも、気分が崩れたときは豹変します。
些細なことでスイッチが入り、何時間でも怒り続けることもあります。
その矛先が子どもに向かうと、私は心が張り裂けそうになります。
怒りのコントロールができないのもうつ病の症状だということを、頭ではわかっているけど、、、
「もうやめて」
「言い方がきつすぎるよ」
と止めようとすると、今度は怒りが私に向いて、夫婦の言い争いに発展してしまう。
子どもにはまだ、夫が“休職している”ことも、“うつ病”であることも伝えていません。
だからこそ、子どもはさらに混乱しているように見えました。
■「バンッ」と閉まる大きな音
夫が怒って家を出ていくとき、乱暴に閉める扉の音が響きます。
バンッ!という音が、心臓に直接響くようで、私は思わず肩をすくめてしまいます。
子どもも、一瞬動きを止める。
この音ひとつで、家全体が“緊張状態”になるんです。
ただの生活音――のはずなのに、
その音に込められた感情が鋭く突き刺さってくるから、怖いんです。
■予定が一瞬で壊される日々
機嫌がよかったときに、「これ一緒にやろうか」と決めた家族の予定。
子どもとの外出、ちょっとした買い物、夕飯の支度の手伝い――
でも、突然機嫌が変わると、全部なかったことにされてしまう。
「もうやらない!」「知らん!」「お前がやれよ」
そして結局、私が全部背負うことになる。
子どもの期待、家の用事、崩れた空気のリカバリーまで。
何に怒っているのか分からない。
でも、怒っていることだけは伝わってくる。
その“空気”に、私はいつも振り回されている気がします。
■「言わない」ことが、必ずしも守ることではない
子どもは大人が思っている以上に敏感です。
「お父さん、なんだか怖い」「お母さん、いつもピリピリしてる」
そんな空気を肌で感じて、言葉にできない不安をため込んでいるかもしれません。
ある児童心理士の方が言っていました。
「“全部を正直に伝える”のではなく、“子どもが理解できる範囲で安心させる”ことが大切」
たとえば、こんなふうに伝えるのはどうでしょう。
「お父さんはちょっと疲れていて、元気が出ない時があるんだよ」
「でも、それはあなたのせいじゃないし、すごく大事に思ってるからね」
「お父さんが怒っているときは、ママがちゃんと見てるから大丈夫」
子どもに「状況をコントロールできない不安」を持たせないこと。
これが、子どもを守るために私たちができる“伝え方”のひとつなのだと思います。
■子どもと自分を守る具体的な工夫
気分が不安定な大人が家にいると、家全体が“地雷原”のようになります。
だからこそ、私は「安全基地」を意識してつくっています。
▼ 子どものためにできること
- 夫が怒っているときは、物理的に距離を取る(別室で過ごしたり、子どもと出掛ける)
- 子ども専用の“安心スペース”を作る(おもちゃ・ぬいぐるみ・音楽)
- 子どもの気持ちを聞く時間を持つ
▼ 自分の心を守るためにできること
- 日記やメモで「自分の気持ち」を吐き出す
- カウンセリングや支援団体にオンラインで相談
- 怒りが向いたときの「逃げ場所」を事前に用意しておく
■「がんばらなくちゃ」じゃなくて、「守られていい」
私はずっと、病気のせいなんだから仕方ない。我慢しないといけない。と思っていました。
でも、それでは長くは続かない。私が壊れてしまうと、子どもも一緒に不安定になってしまう。
だから今は、少しだけ考え方を変えようとしています。
「逃げてもいい」
「言い返してもいい」
「助けを求めてもいい」…そして、「自分を守ることは、子どもを守ることにつながる」
▼まとめ:矛盾の中で揺れるあなたへ
- 「いいパパ」と「怒り続けるパパ」――その間で悩んでいい
- 子どもには、安心できる言葉と空間を与えよう
- 自分のために、逃げ場・話し場・休み場を持っていい
- “助け”は甘えじゃなく、戦略です
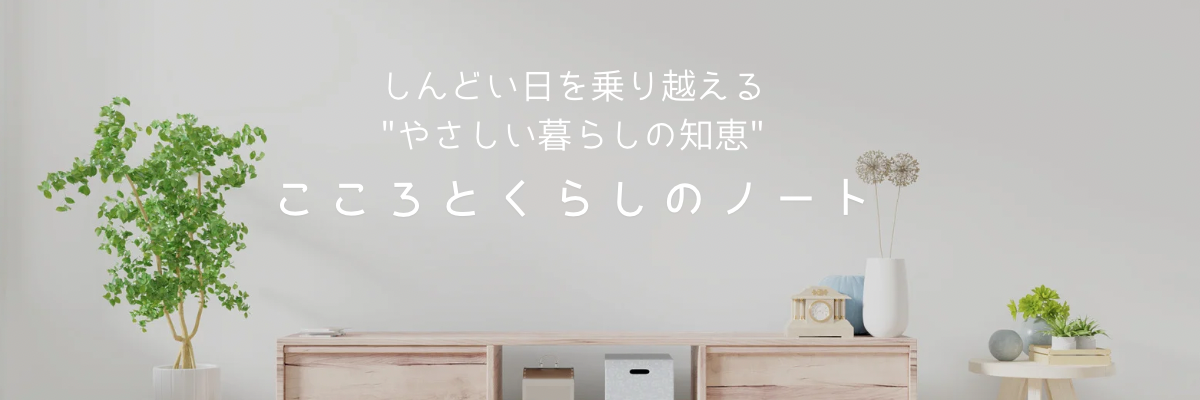




コメント